お知らせ
あいむすまいる!『介道をゆく』スペシャルインタビューvol.6 -おうみ在宅クリニック 鎌田先生
2025.09.07

2023年守山市に開業した『おうみ在宅クリニック』は、名前の通り訪問診療に特化した診療所。院長の鎌田泰之さんが病棟の外科医から在宅医療のフィールドへ踏み入れた、その転換の中に見える地域貢献へのまなざしを紐解いていきます。聞き手である米津と共通するのは、その社 会への影響を縦へ横へと伸ばしながらいかに最大化していくかと日々創意工夫する熱いエネルギーでした。
※介道をゆく・・・株式会社あいむが、地域に根付き活躍する介護・医療・福祉のプロフェッショナルにお話しをうかがうインタビュー企画。主に統括部長でありケアマネジャーであり、社会福祉士養成校で教壇に立つ米津達也が対談する。新たな視点で地域に必要な場所やサービスを立ち上げ、切り拓く人たちの英知や苦労を聞き出し、ともに未来について考えます。
米津:鎌田先生が医師になろうと思ったきっかけは何だったんですか?
鎌田:元々、小学生の頃からずっとサッカーをやっていてコーチになりたいと思っていたんですよ。それならスポーツ医学の知識があるといいかなと思って医師を目指したのですが、大学5年生の時に、誰かにサッカーを教えるより自分の腕一本で生きていきたいという思いに変わって、整形外科医を志しました。このクリニックを開設する前は消化器外科医だったんですけど「手術が上手くなりたい」というのがモチベーションでしたね。
米津:そこから在宅医療に転換したのはなぜですか?
鎌田:外科医を経て分かったのは、手術はあくまで患者さんを治す手段であって、患者さんはみんな受けなくていいなら手術なんて受けたくないんですよね。でもその手段である手術が目的化して上手くなりたいと思うことに違和感を感じていました。それで、よくよく考えていくと私がサッカーを好きなのも、手術を好きなのも「みんなで成果を出す」ことが好きなんだと気付いたんです。それなら、自分でチームを作ってやってみたいと思い、医者だったら開業するしかないと思い至りました。

鎌田:それと、大学院生の時に初めて在宅医療に出会って、これは社会に求められていることだと感じたんですよね。実際、政府も在宅医療を推進していますし、社会に貢献出来て、自分の好きなことが出来るならというのが動機です。もっとかっこつけて言えば、僕自身が好きかどうかというより、僕が単独で手術して直せるのは担当した患者さん一人ひとりだけですけど、チームで社会に貢献出来ると、もっと大きな影響になると思ったんですね。僕自身が社会に対してできる貢献を最大化したいんです。
米津:なるほど。私は組織に属するケアマネジャーなので、やはり一人で独立開業するよりはリスクが少なく、安定して仕事をしていけると思うんです。病院勤めを手放して開業するということに不安はなかったんですか?
鎌田:それはもちろんありますよ(笑)でも、よく言われるように「変化しないことの方がリスク」でもあるじゃないですか。どんな環境でもそうだと思うんですけど、待っていても躍進的に変わっていく場所の方が少ないですし、同じ環境にい続けることの閉塞感はぬぐえない。開業したら、こうして米津さんと新しい人間関係が出来たりとか、新しい可能性がありますよね。
米津:私は開業ではないのですが、逆に5年前あいむに入社するまでずっと一人でケアマネジャーをやっていたんですよ。ケアマネを始めた当初から一人だったので、上司から教わることもなく、自分で仕事内容を解釈しながら運営して7年くらい続けました。そういう一匹狼が自分の性にも合いますし、当時を知る人たちからはあいむで管理職をやっている今の私はらしくないよねと言われます(笑)。確かに実際、組織をマネジメントすることは窮屈な部分もありますよね。でも鎌田先生がおっしゃったように、私が一人でケアマネをして社会に還元できる事はたかが知れていますし、自分が持っているスキルを誰かに伝えていけば、その後の社会を作る人たちが社会に還元してくれるかなと思って、動いているところはあります。
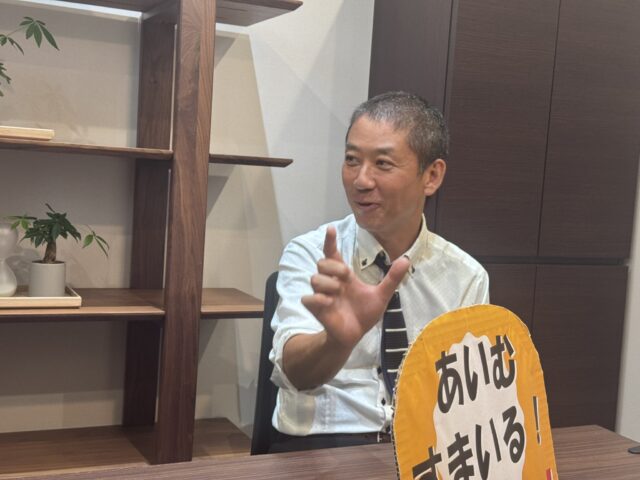
米津:チームの話で言うと、在宅医療はやはり病院とはチームの在り方が違うじゃないですか。患者さんごとに担当のケアマネが違ったり、介護側との連携は関わる人の数も膨大になると思うんですけど、その辺りはどうですか?
鎌田:外部との連携は、やはりそれぞれ所属されている事業所も違うので、まだチームと言えるところまで意識するには至っていないですね。そもそも医者がチームリーダーとして統率するべきなのかとも思いますし、ケアマネジャーさんの権限の部分とか、良い距離感を探りながら……。でも、連携することは重要だと思うので、今は勉強会を一緒にやらせてもらったり、チームになる前段階かもしれません。
米津:恐らく、介護保険制度が始まった20年前からケアマネジメントに携わっているケアマネには、医師からのトップダウンで物事を進めるという刷り込みがあると思うんですよ。鎌田先生や今の医師の方々はコミュニケーションの取り方も大きく変わっているはずですけど、ケアマネ側がアップデート出来ていないということはありそうですね。これから先、ケアマネも世代交代すれば医療チームとの連携が変わるんだろうなとは思います。この関係性のアップデートが先行して成功しているのが訪問看護だと思います。若い世代が訪問看護の事業所を立ち上げて、うまく介護チーム側に発信してきた努力の結果、コミュニケーションの取り方も変わってやりやすくなったところはありますね。
鎌田:現状は、ケアマネジャー・訪問看護師・医師がいたら、訪問看護師さんが仲介役になってくれていますよね。
米津:これからもっとICTのシステムを上手く使って、まずその3者だけでも情報共有していければ、コミュニケーションの在り方がかなり変わるんじゃないかと思います。
米津:ここまで、チームの話や介護領域との連携についてお話を聞いてきましたが、患者さんに対してはどうですか?オペ室や外来とは全く違う『訪問診療』という関わり方で、実際に様々な症例を診ていて思われることを教えてください。
鎌田:そうですね、うちは患者さんの平均年齢が90歳ぐらいなので……。
米津:そんなに高いんですか!?
鎌田:はい。クリニックのキャッチコピーとして「元気でいたい」と「良い最期を迎えたい」という2つの思いにいかに応えるかをミッションにしているんですけど、例えば、急に人工呼吸器につながれて亡くなった患者さんのご家族は、やはり後悔していることが多いんですよ。いざそうなった時に話し合いを持てずに最期を迎えることが多いので、ご本人の意思をちゃんと確認することと、家族の思いを汲み取るということがどちらも大事ですし、随分変わったなと思いますね。外科医だったころは、死というのは心臓が動かなくなることだとか、もっとドライに捉えていたと思うんですね、仕方がないことだと。もちろん、医学的に痛みを感じないように最期を迎えてもらうとか、そういうことも大切なんですけど。
米津:我々もクライエントとの関わりは、ご本人がお亡くなりになってケースが終了ということは多いのですが、先生方はやはり目の前で人が亡くなられるし、その後の対応もしないといけないですよね。きっと我々とは命との向き合い方が違うんだろうなと思うんですけど、鎌田先生が思う「良い最期」とはどういうものなんですか。
鎌田:誰かの死に対して意味を与えてあげないと、ただただ死が悲しいものになると思うんです。それで、患者さん自身も家族も「次の世代にバトンをちゃんと渡せた/もらえた」という感覚が得られることが、死の意味になるんじゃないかと思うんです。患者さんに対して、親がいたから自分がいると認識出来たとか、よくしてもらえたなと感謝しているとか、そんな風に上の世代の方々がいたから私たちがいて、次の世代がいるんだという意味を与えていくことが、良い最期なんじゃないかなと思うようになったんですよ。
米津:鎌田先生と関わる患者さんは非常に大きなご病気だったり、残された時間もたくさんあるわけではないけど、最期は家で過ごしたいと思われる方が多いのだと思いますが、その有限の時間の中で、患者さんやご家族に対してのアプローチで心掛けていることはありますか?例えば、現実を直視しながら淡々と病状の説明をすることも必要だと思いますし、受け止めてこの先に進んでいくためにというか。
鎌田:人によって様々な考え方があると思うので、どういう考えの人なのかは探っていますね。諦めきれないという気持ちもあるでしょうし、逆に年齢的に色んな治療を望まない方もいるし、病状そのものの理解が難しい方もいる。何が何でも助けて欲しいと思う人もいる中で「もう治療法はありません」とズバリ言う医者もいていいと思うんですけど、僕はそれを言えないタイプなので……探るというか、どういうお考えなのかなと予測して合わせていきます。でも、医者が一番してはいけないのは「選択肢がAとBあるんですけど、どちらにするか決めて下さい」と全て委ねてしまうことだと思うんです。せめてこちらがいいですよと伝えてあげた方が良い。Aを奨めてもBにしたいですとおっしゃるならそれは良いんですけど。だから誘導ではないですけど、医療の経験は圧倒的に医者の方が多いので、どちらが絶対良いというのは持っているので、それは伝えるべきだと思います。
米津:確かにそうですね。在宅医療で人の生活に関わっていくことは、病院時代に比べると難しいですか?
鎌田:難しいですね……!訪問すると自宅が見えて、人となりが分かりますよね。外来の診察室は患者さんにとってアウェイですし、緊張もされていて、そんな中で診ていて分かっていない部分もあったんだろうなと思います。
米津:私は社会福祉士の養成校で12年ほど非常勤講師をしてるんですけど、先日、卒業生がインターンで弊社に来たんです。その卒業生はソーシャルワークの授業で私が事例を話す時に、いつも「先生、その後答えはどうなったの?」と聞いてくる。その子と一日一緒に実際に現場をまわってみて、体験してみてどうだったか聞いてみると、やっぱり「難しい」「分からない」だったんです。それはそうです、人の生活に関わることに正解なんかないし、分からないんですよ。でも、分からないものだということが分かっただけでも、その卒業生はひとつ得るものがあったんじゃないかと思うんです。そういう「人の生活」という答えのないものに関わり続けるのが対人援助職の仕事なんですけど、手術すると治るという成果のある世界ではなく、正解のない世界というフィールドに立って、医師だろうがケアマネだろうが同じラインでお互いに話を突き詰めながら、クライエントにとってより良い生活・より良い最期とはこうだよね、とお互いに積み上げていくのが、きっとチームワークなんだろうなと思います。

米津:これから少子高齢化がますます進み、みんなが病院で亡くなるわけでも施設に入れるわけでもなくなると、尊厳という部分だけでなく住み慣れた家で最期を過ごしたいという思いは高まるのかなと思います。訪問診療のニーズがさらに急加速するであろう中で、3年後もしくは5年後、鎌田先生が思い描いておられる未来の展望はどのようなものですか?
鎌田:具体的にこうなりたいというのはないんですよね。というより予想してもそうならないというか(笑)こうして在宅医療に関わっていることも全然予想していなかったので。ただ、いつも従業員には、目的と目標を混同しないで下さいとは伝えています。目標というのは患者さんの数とか売上げみたいな、数値化して達成可能なことですよね。その目標を目的にしてしまうと間違ったことが起きるので、ちゃんと目的を定めてそのためにやっていくということは常々言っています。
あとこれは、クリニックというより個人的にかもしれないですけど、この事業を通じて前の世代の方々からバトンを受け取って、僕ら現役世代が次の世代にバトンを渡すというのがミッションだと思っているので、そのためにどうするのかを考えていく。ここからブレさえしなければ、事業が大きくなって社会に対する貢献が大きくなればいいということだし、ここからブレていくことががあれば、それはやめた方がいい。例えば、クリニックに絵本を置いてるんですけど、小学生向けに命の授業みたいなものもやっていきたいなと思うんです。あるいは、中学生の体験授業を受け入れてみようと思ったり、在宅医療を通じてもっと若い世代に対しても貢献できる範囲を広げていけたらなぁと、そういうことを淡々とやりたいなと考えています。
米津:次の世代にどのようにうまくバトンを渡していくのか、その工夫をするのも我々の仕事ですよね。
鎌田:だから、クリニックの内装もお洒落にしたり、患者さんの情報管理するのにNotionを使ったり、やっぱり見た目の格好良さに惹かれる人もたくさんいらっしゃるので、そこも大事にしないととは思います。今、Instagram用に撮影もしていますけど、本当はこういうのも緊張するしすごく苦手で(笑)。でも、チームを率いてそんなこと言ってる方がダサいなと思うし、若い世代に伝えるためにインスタも積極的に挑戦します。
米津:そうなんですね!?でもチャレンジする風土は大事ですよね。弊社の代表も、失敗してもいいじゃないか、何もやらない方が嫌だと言うんです。だから、私もこうして取材に出たり、ユーチューバーにもなったり(笑)色んな事をやらせてもらえている。私が前に出ることで、あいむの従業員が自分もやってみたいと思ってくれれば、そういうバトンの渡し方もあるかなと最近は思いながらやっています。お互いにそんな感じで頑張っていきましょう!
あいむすまいる!第91号 2025年9月7日発行
あいむが発行する広報誌あいむすまいる!は毎月第一日曜日守山市、野洲市、甲賀市、大津市、栗東市に80,000部配布しております。
あいむのInstagram